『木(The Tree)』(H.P.ラヴクラフト著)の解説
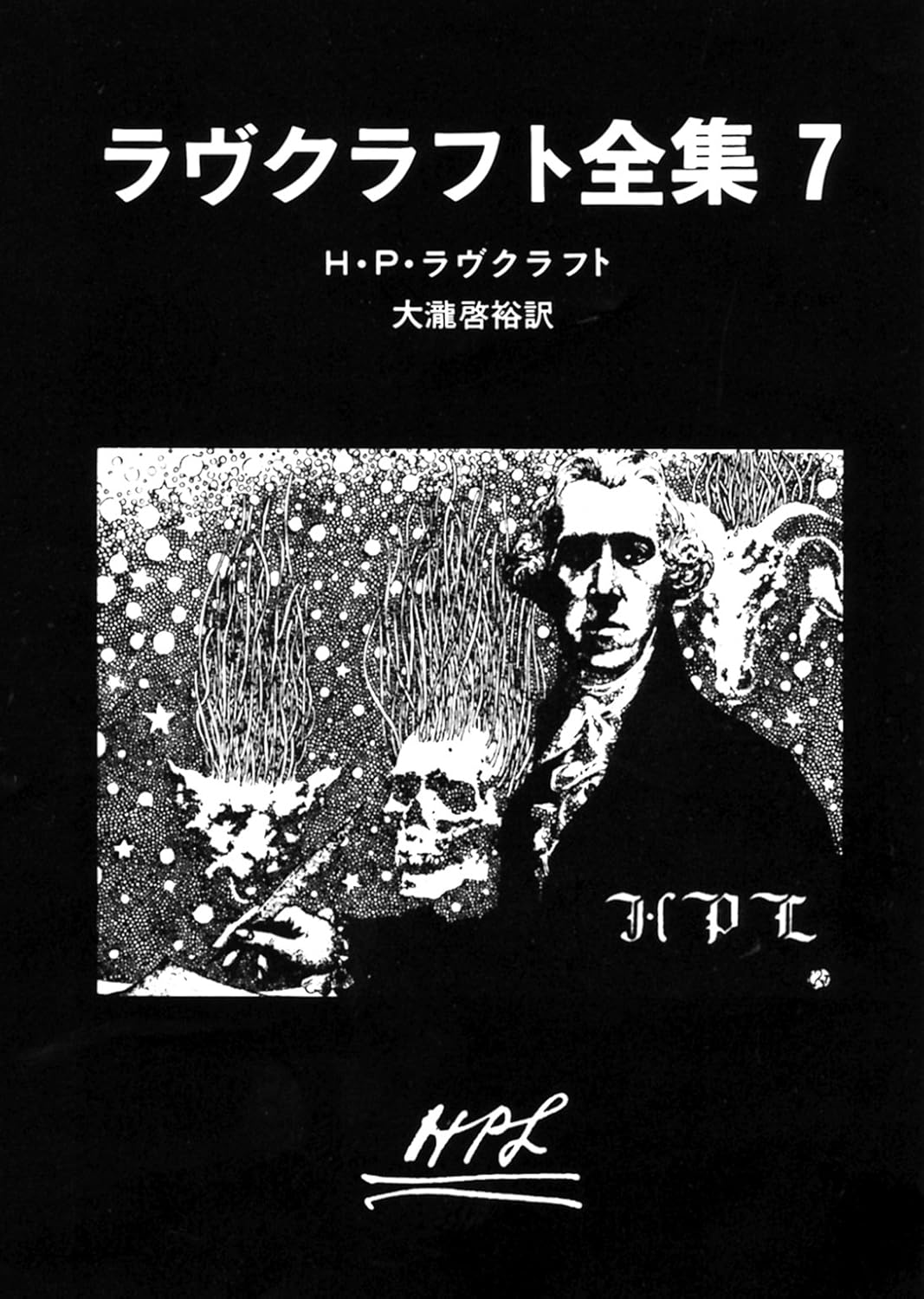
『木(The Tree)』は、H・P・ラヴクラフトが1920年に発表した短編であり、彼の中では比較的簡潔かつ寓話的な作風を持つ作品である。
古代ギリシャ風の舞台設定と、芸術・友情・嫉妬・死・自然への畏怖といったテーマが織り込まれており、最後には因果応報とも超自然的報復とも受け取れる展開を見せる。
創元推理文庫の『ラヴクラフト全集7』に収録されている。
目次
注意
読者の体験を損なう可能性があるため、本解説を読む前に先に物語を読んでおくことを強く推奨する。
書籍の表紙以外に掲載しているイラストはあくまで本ブログによる創作物であり、公式に発表されているものではない点に注意して頂きたい。
物語の概要

物語の舞台は、古代ギリシャのアルカディア地方、マエナルス山の斜面である。
そこにはかつて彫刻家カロース(Kalos)とムーシデス(Musides)の二人が暮らしていた。
二人はともに名声高い芸術家であり、友情と協力によって知られていた。
彼らの住居は美しいオリーヴの林に囲まれ、各自の作業室を持ちながらも、芸術と親愛の絆を深く共有していた。
ある時、シュラークーサエ(Syracuse)の僭主が使者を送り、「運命の女神テュケー(Tyche)」の像を造るよう依頼する。
それぞれの像が競作として制作されることとなり、二人は作業に打ち込むが、時を同じくしてカロースが病に伏せるようになる。
カロースの病は次第に悪化し、死期が近づいたある夜、彼はムーシデスに「自らの墓の傍らに、オリーヴの林から特別な枝を埋めてほしい」と遺言する。
彼は林の「見えざるもの」と交信していたような描写がなされ、墓への小枝埋葬は何らかの神秘的な意味を含んでいる。
カロースの死後、ムーシデスは深い悲しみに暮れながらも、テュケー像の制作に励む。
そして三年後、ついに完成した像をシュラークーサエに送る準備が整った直後、突如として大嵐が起きる。
嵐の翌朝、彫刻家の住居は完全に崩壊し、ムーシデスも、彫像も、痕跡すら残されていなかった。
代わりに、カロースの墓の脇から生えた異様な巨大オリーヴの木だけが残り、その枝はまるで意思を持つようにムーシデスの作業場を圧し潰していたのである。
登場人物
カロース(Kalos)
精神性が高く、自然や霊的な存在とつながる内向的な芸術家。
オリーヴの林で「見えざるもの」と交信し、現世の名声よりも、死後の神秘に重きを置いている。
死後、その存在が自然を通じて復讐の媒介となる。
ムーシデス(Musides)
より現実的・享楽的で社交的な性格の彫刻家。
カロースを深く慕っていたが、彼の死後、芸術に没頭するうちに自らの運命の歯車に巻き込まれる。
シュラークーサエの僭主
名前は明かされないが、芸術を愛する強大な権力者。
彼の依頼が物語の悲劇的展開の起点となる。
地名
マエナルス山
神話的な霊性と野生の象徴として描かれる。
パーン神や森の霊(ファウヌス、ドリュアス)の領域であり、自然の神秘と超自然的報復の場でもある。
テゲア(Tegea)
文明的な都市国家の代表。彫刻が完成された場所であり、カロースとムーシデスの住居があった地域。芸術と自然のあわいに位置する。
シュラークーサエ(Syracuse)
遠方の強国で、政治的権力と芸術への欲望を象徴する都市。
ここへの使者の派遣が物語を動かす。
解説
『木』は、芸術と自然、精神と物質、友情と嫉妬、そして死と復讐といったテーマが複雑に絡み合った作品である。
一見すると、カロースとムーシデスの関係は完全な友情によって結ばれていたように描かれるが、ラストにおけるムーシデスの消失は、カロースの意志あるいは精霊的存在による超自然的報復であることが暗示される。
特に象徴的なのは、「墓に埋められたオリーヴの枝」から育った異常な木であり、それは単なる植物ではなく、死者の意思や神の力が宿った呪具のような存在である。
人間の栄光と芸術の努力が、自然の神秘的力の前に無力であるという皮肉な構図が描かれている。
また、ムーシデスが最後に消え去るという描写は、「美や栄光を追い求めても、真に残るものは自然の力と記憶だけである」という、儚さと運命を感じさせる締めくくりとなっている。
本作は、恐怖小説というよりもむしろ寓話的な悲劇として読むべきラヴクラフトの作品であり、彼の中でも異色の短編である。