『ダゴン(Dagon)』(H.P.ラヴクラフト著)の解説
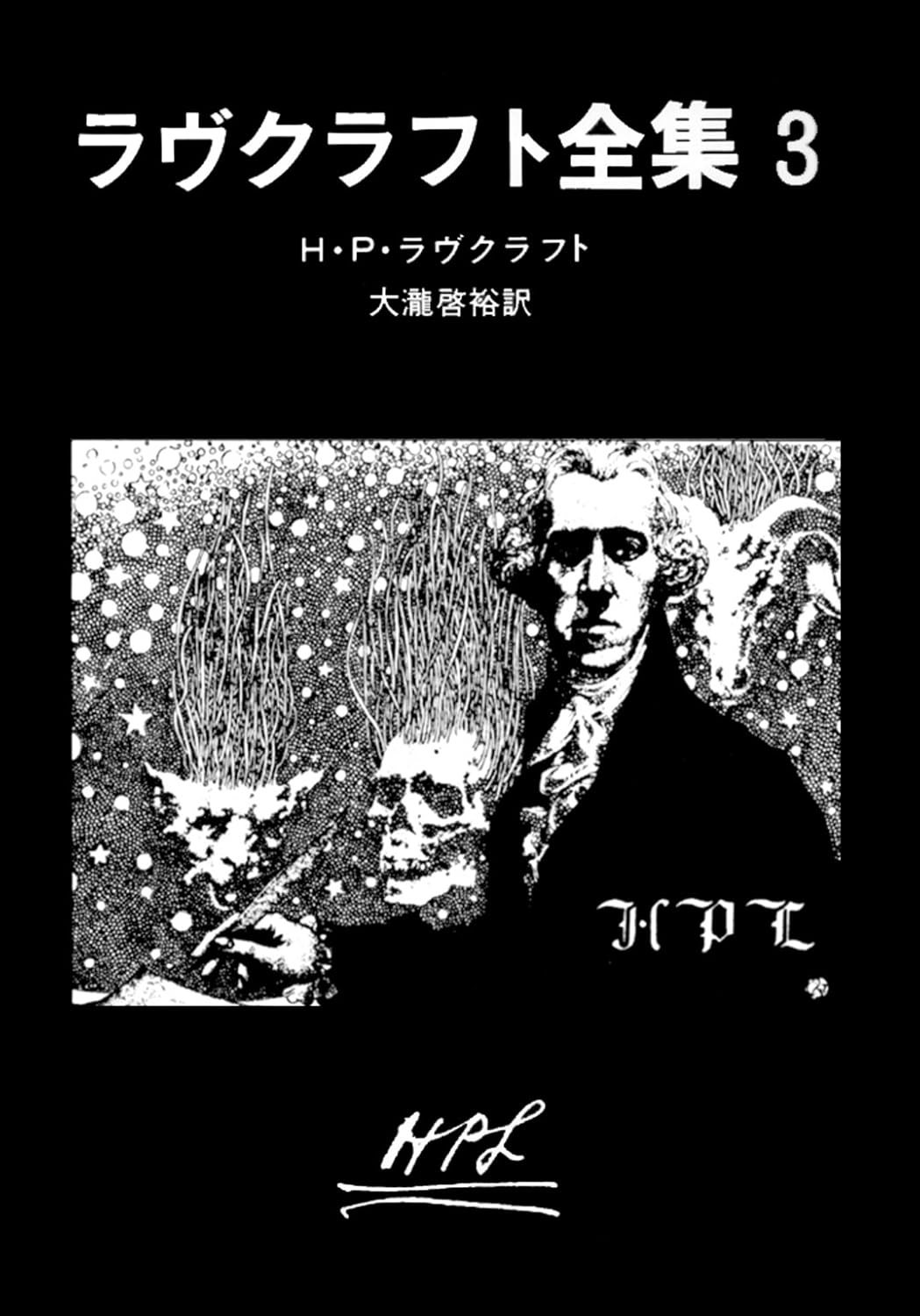
『ダゴン』は、H.P.ラヴクラフトが1917年に執筆した短編小説であり、後の「クトゥルフ神話」の原点とも称される作品である。
創元推理文庫の『ラヴクラフト全集3』に収録されている。
目次
注意
読者の体験を損なう可能性があるため、本解説を読む前に先に物語を読んでおくことを強く推奨する。
書籍の表紙以外に掲載しているイラストはあくまで本ブログによる創作物であり、公式に発表されているものではない点に注意して頂きたい。
物語概要

物語は、語り手である無名の男が、自身の狂気に至る体験を告白する形で語られる。
この男は、第一次世界大戦中にドイツ軍の襲撃を受け、漂流の末に、太平洋のどこかで突如現れた異様な陸地にたどり着く。
彼はそこに広がる地獄のような泥の平原をさまよい、やがて巨大な碑石のような構造物と、それに刻まれた異形の海洋生物のレリーフを発見する。
そして、突如として現れた巨大な魚人のような存在に遭遇し、正気を失った彼は、モルヒネにすがりながら現実から逃避するようになる。
物語は、彼が最期の時を迎えようとする瞬間に、再びその存在が訪れたかのような描写で幕を閉じる。
登場人物
語り手(主人公)
名前は明らかにされていない。
元は商船の船荷監督であったが、ドイツ軍に拿捕された後、ボートで脱出し、恐怖の体験をすることになる。
彼は理性的な人間であったが、その体験以降、モルヒネに溺れ、精神を病んでしまう。
海中の怪物(魚人あるいはダゴン)
語り手が深淵の割れ目で見た、巨大な鱗に覆われた忌まわしい存在。
碑石に彫られていた海洋生物と同種である可能性があり、古代の神と同一視される。クトゥルフ神話では、この存在が後に「ダゴン」と呼ばれるようになる。
民族学者
語り手が一度だけ接触した学者。ダゴンに関する知識を得ようとするが、表面的な理解しか示さなかった。
地名・設定
太平洋の正体不明の海域
語り手がドイツ軍から脱出したあとに漂流し、異様な陸地に流れ着いた場所。火山活動か何かによって隆起したと語られるが、通常の地理学では説明できない。
黒い軟泥の平原
海底が隆起して現れたと思われる地域。腐敗した海洋生物の死骸が散乱し、不気味な静寂に包まれている。
ここで語り手は人知を超えた恐怖を経験する。
巨大な碑石
割れ目の奥に立つ、謎めいた構造物。
未知の象形文字と海の怪物を描いた浮彫が施されており、かつての崇拝や儀式の痕跡を感じさせる。
これは「深きものども」の信仰の証とされる。
解釈と意味
この作品は、人間の理性が宇宙的恐怖によって崩壊していく様を描いたものである。
語り手は文明の枠を超えた存在と遭遇し、それに対して無力であることを痛感する。
作中では「ダゴン」という名が直接的に怪物と同一化されるわけではないが、ラヴクラフトの他の作品群と照らし合わせることで、この存在が古代の海神ダゴンに通じるものとして解釈されている。
『ダゴン』は後の「インスマスの影」などで展開される深きものどもの原型ともいえるモチーフを初めて提示した作品であり、クトゥルフ神話における「深海」「古代神」「人間の狂気」といった主要なテーマが凝縮されている。