『眠りの壁の彼方(Beyond the Wall of Sleep)』(H.P.ラヴクラフト著)の解説
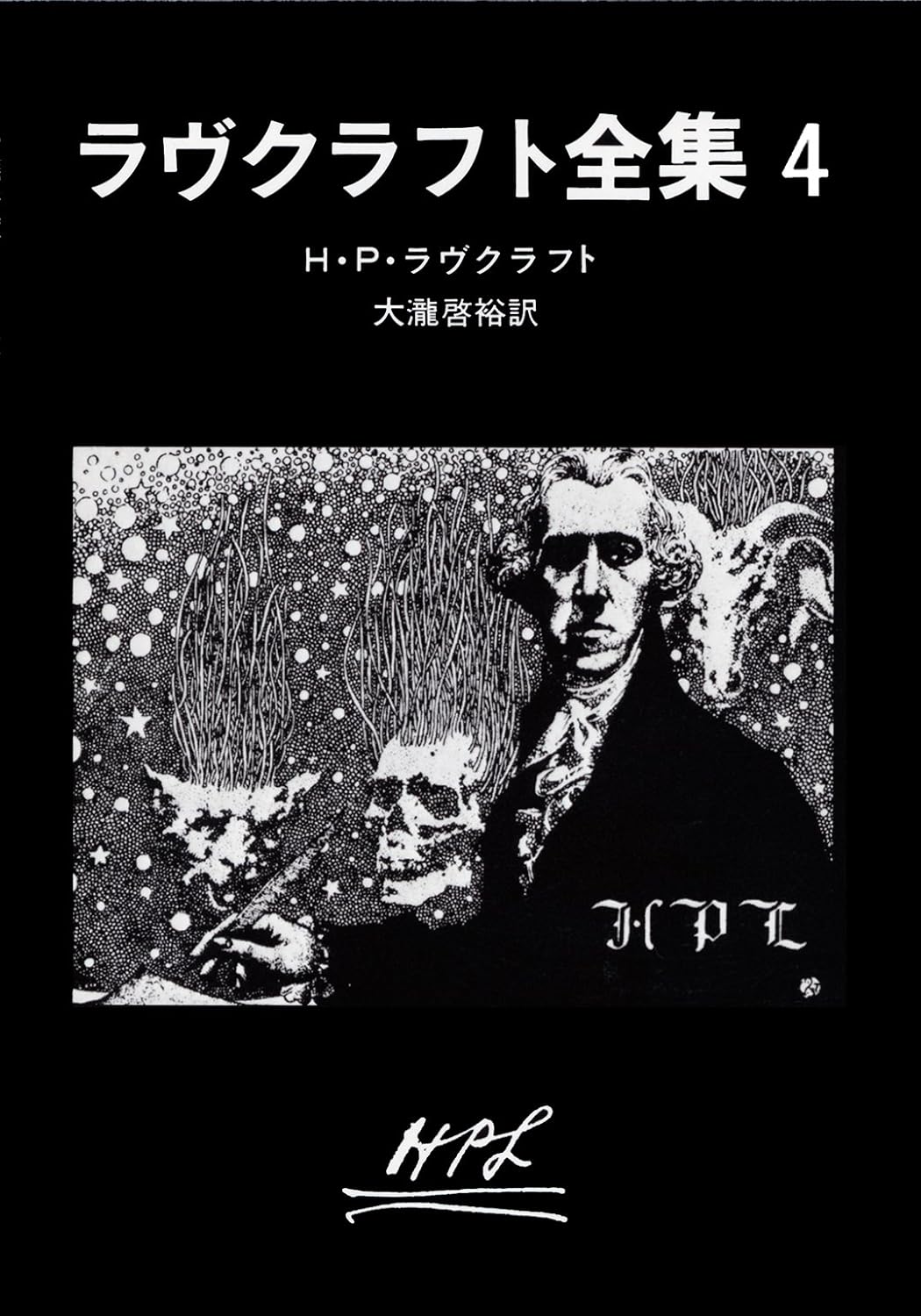
『眠りの壁の彼方(Beyond the Wall of Sleep)』は、H・P・ラヴクラフトが1919年に執筆した短編小説である。
本作は、人間の夢と宇宙的存在との関係をテーマに、科学・精神・宇宙的視点を交差させた実験的な作品である。
創元推理文庫の『ラヴクラフト全集4』に収録されている。
目次
注意
読者の体験を損なう可能性があるため、本解説を読む前に先に物語を読んでおくことを強く推奨する。
書籍の表紙以外に掲載しているイラストはあくまで本ブログによる創作物であり、公式に発表されているものではない点に注意して頂きたい。
物語の概要

物語の語り手は、精神病院に勤務する若き医師であり、精神異常の受刑者ジョー・スレイターの扱いを任されることになる。
スレイターはニューヨーク州のキャッツキル山地で暮らしていた凶暴な農民で、殺人を犯し、異常な発作と意味不明な言動から精神病院に収容された。
彼の発言には、光、飛翔、宇宙といった言葉が頻出し、常軌を逸しているようで、どこか別世界の啓示を感じさせた。
語り手は自作の装置「テレパシー・ラジオ」を用いて、スレイターと思考の伝達を試みる。
その結果、語り手の精神はスレイターの中に潜む異次元の存在と接触を果たす。
スレイターの身体は、地球外の高次の存在にとって一時的な「牢獄」に過ぎず、語り手と接触した存在は、光輝く宇宙を旅する「夢の存在」であった。
その存在は、語り手に対し、自らが地球の圧政者と戦うため、さまざまな姿に転生しながら宇宙をさすらっていること、そして語り手自身も夢の世界でともに旅した「光の兄弟」であることを明かす。
スレイターの死とともにその通信は途絶えるが、語り手は自らの夢の中で確かに“彼方”の世界を見たと信じるようになる。
登場人物
語り手(主人公)
若き精神病院職員。
科学と超常の交差点で、夢と宇宙的真理に触れる人物。
終始冷静だが、物語の終盤で次第に自身の常識が揺らぎはじめる。
ジョー・スレイター
キャッツキル山地の粗暴な農夫。
殺人事件を起こして収容されるが、発作時に宇宙的存在と一体化していた。
彼の身体は高次の存在にとっての一時的な器であった。
夢の存在
スレイターを媒体として語り手と通信した宇宙的実体。
語り手の「光の兄弟」であり、時間や空間を超越して活動する。
「赤いアルクトゥルス」や「木星の五番目の月」を旅していたことが語られる。
地名・設定
キャッツキル山地
スレイターの出身地であり、自然に囲まれた人里離れた場所。
ラヴクラフトにとって、土俗的で原始的な人物像の象徴となっている。
精神病院
スレイターが収容され、語り手との通信実験が行われた場所。
文明と科学の象徴であるが、その内部で異界への扉が開かれる。
眠りの壁(The Wall of Sleep)
物理的世界と夢や宇宙的世界との境界を象徴する言葉。
通常は超えられない障壁だが、語り手はスレイターを通してそれを超越する。
考察
本作はラヴクラフトの初期作品の一つでありながら、のちの「クトゥルフ神話」につながる宇宙的恐怖(Cosmic Horror)の萌芽が見られる。
スレイターは「堕落した田舎者」として描かれながらも、その中に宇宙的存在が宿っていたという設定は、後年の「狂気の山脈にて」「銀の鍵の門を越えて」にもつながるテーマである。
また、夢と現実のあいだの曖昧な境界、そしてそれを科学の手法で超越しようとする試みは、知性と霊性、理性と狂気が交錯するラヴクラフトらしい構造である。
タイトルの「眠りの壁」は、我々が日々経験する「夢」が、単なる心理現象ではなく、より高次元の現実との接触点であるという示唆を込めた表現である。
本作は決して構造的に洗練された作品ではないが、夢の中に真理があるという逆説的主張、そしてその先に広がる広大な宇宙のヴィジョンは、後のラヴクラフト作品の原型として重要な意義をもつ。