『月の湿原(The Moon-Bog)』(H.P.ラヴクラフト著)の解説
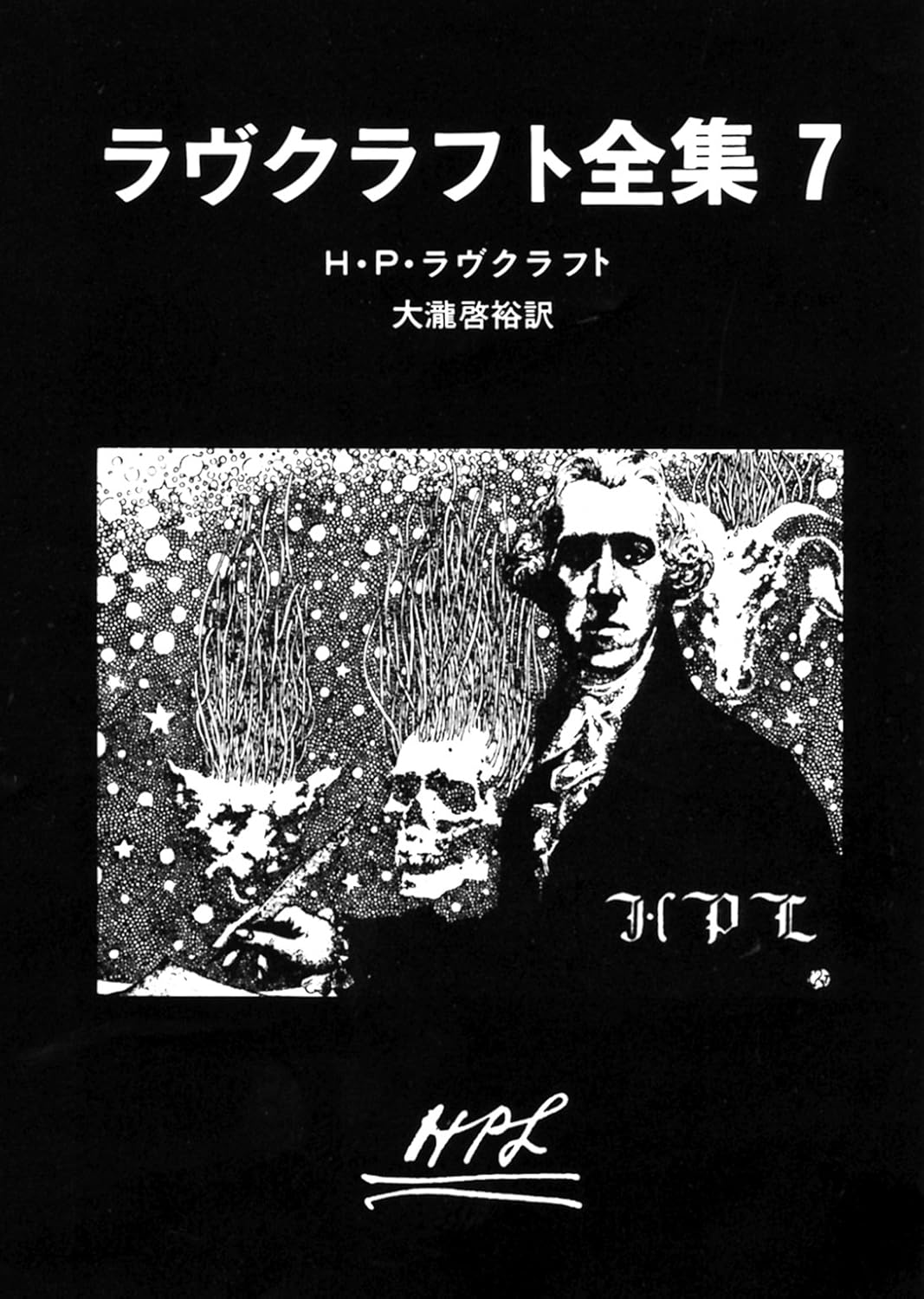
『月の湿原(The Moon-Bog)』は、H・P・ラヴクラフトが1921年に執筆した短編小説であり、古代への冒涜とその報い、そして自然と民間伝承への無理解を主題とする怪奇譚である。
アイルランドを舞台に、ヨーロッパ的土着信仰と土壌の神秘を扱った作品であり、後年のクトゥルフ神話とは異なる伝統的なゴシック・ホラーの色彩を帯びている。
創元推理文庫の『ラヴクラフト全集7』に収録されている。
目次
注意
読者の体験を損なう可能性があるため、本解説を読む前に先に物語を読んでおくことを強く推奨する。
書籍の表紙以外に掲載しているイラストはあくまで本ブログによる創作物であり、公式に発表されているものではない点に注意して頂きたい。
物語の概要

物語は、語り手が古い友人デラポア(Delapore)の破滅について語る形式で始まる。
デラポアはアイルランドの古い家系の出自であったが、長らくアメリカに暮らしていた。
彼はある時、祖先の土地であるアイルランド西部の古城と周囲の湿原を相続し、「近代化による開発」を目的にその地に戻る。
かつては栄えたこの土地には、長年にわたって不気味な伝説と恐怖が語り継がれていた。
湿地帯では人々が奇妙な幻を見、満月の夜になると、忌まわしいものが這い出すと信じられていた。
現地の農民たちは、湿原の奥に何かが「棲んでいる」と信じており、迷信深く、その地を恐れていた。
しかしデラポアはそのような伝承を「迷信」として一笑に付し、土地の開発に着手する。
彼は地元の住民の多くを解雇し、ギリシャやイタリアから労働者を輸入して大規模な掘削を始めた。
やがて湿地の地下からは、古代の神殿跡と奇怪な石像が発見され、さらに掘り進めたことで、何かを「目覚めさせた」ことが暗示される。
ある満月の夜、デラポアの古城では祝宴が開かれていたが、その最中、外では月明かりの中から不気味な霧と光が湿地から立ち昇り、恐るべき咆哮が響き渡る。
逃げまどう労働者たちは次々と姿を消し、ついにはデラポアもその霧のなかに呑まれて行方不明となる。
数日後、語り手が現地に赴いたときには、労働者のほとんどが失踪または発狂しており、湿地は静まり返っていた。
ただ一つ、夜になると月の光の中で、無数の幽霊のような影が湿地をさまよっているのが見えるという――それは、永遠に呪われた魂たちであるとも語られている。
登場人物
デラポア(Delapore)
本作の中心人物で古いアイルランド貴族の末裔であり、祖先の地に戻って土地を再開発しようとする。
理性的なアメリカ的合理主義者だが、結末において迷信と伝承の前に破滅する。
なお、同名の人物は『チャールズ・デクスター・ウォードの奇怪な事件』『ネズミの中の闇』など別作品にも登場するが、本作の人物とは直接の関係はないとされる。
語り手(Narrator)
デラポアの友人で、彼の失踪と事件の顛末を目撃し記録する立場にある。
あくまで観察者であり、狂気には陥っていないが、不可解な現象に深い衝撃を受けている。
地元の農民たち
古くから湿地帯の異常に気づいていたが、語り手やデラポアにその恐怖を真剣に受け取ってもらえなかった。
南欧からの労働者たち
異教的な感受性を持ち、湿地の恐怖を敏感に察知していた。
最終的には恐怖によって逃げ去るか、あるいは死・狂気に呑まれる。
地名
月の湿原(The Moon-Bog)
物語の舞台となる広大な湿地帯であり、霧と沼、月光に包まれた神秘と恐怖の場である。
過去にはケルト以前の何らかの神秘宗教の拠点であったことが示唆されており、現代の人間がその禁忌に触れたことにより、復讐を招いた。
デラポア家の城館
古代の伝統と血筋の象徴。
現代的な開発と過去の因習との衝突点であり、物語の破局の場となる。
解説
『月の湿原』は、近代的な合理主義が古代の神秘や自然の摂理に対していかに無力であるかを描いた作品である。
主人公デラポアは、伝承や伝説を「迷信」として退けるが、その結果として破滅を迎える。
ラヴクラフトの他作品と異なり、神話的存在の名は出てこないが、地下に潜む「古きもの」「古代宗教」の暗示は明らかであり、クトゥルフ神話と地続きの空気を感じさせる。
また、本作にはラヴクラフトのアイルランドへの憧れとともに、外国人労働者への懐疑的な視線や、伝統文化の喪失に対する危惧が内包されており、作者の時代的・社会的背景が色濃く反映されている。
「月」というタイトルに象徴されるように、本作は非理性、夜の神秘、そして周期的な復讐の物語である。月光の下で蘇る古の霊魂たちは、自然と人間、過去と現在の間に横たわる深い断絶と報復を象徴しており、幻想と恐怖の余韻を残す短編となっている。