『名状しがたいもの(The Unnamable)』(H.P.ラヴクラフト著)の解説
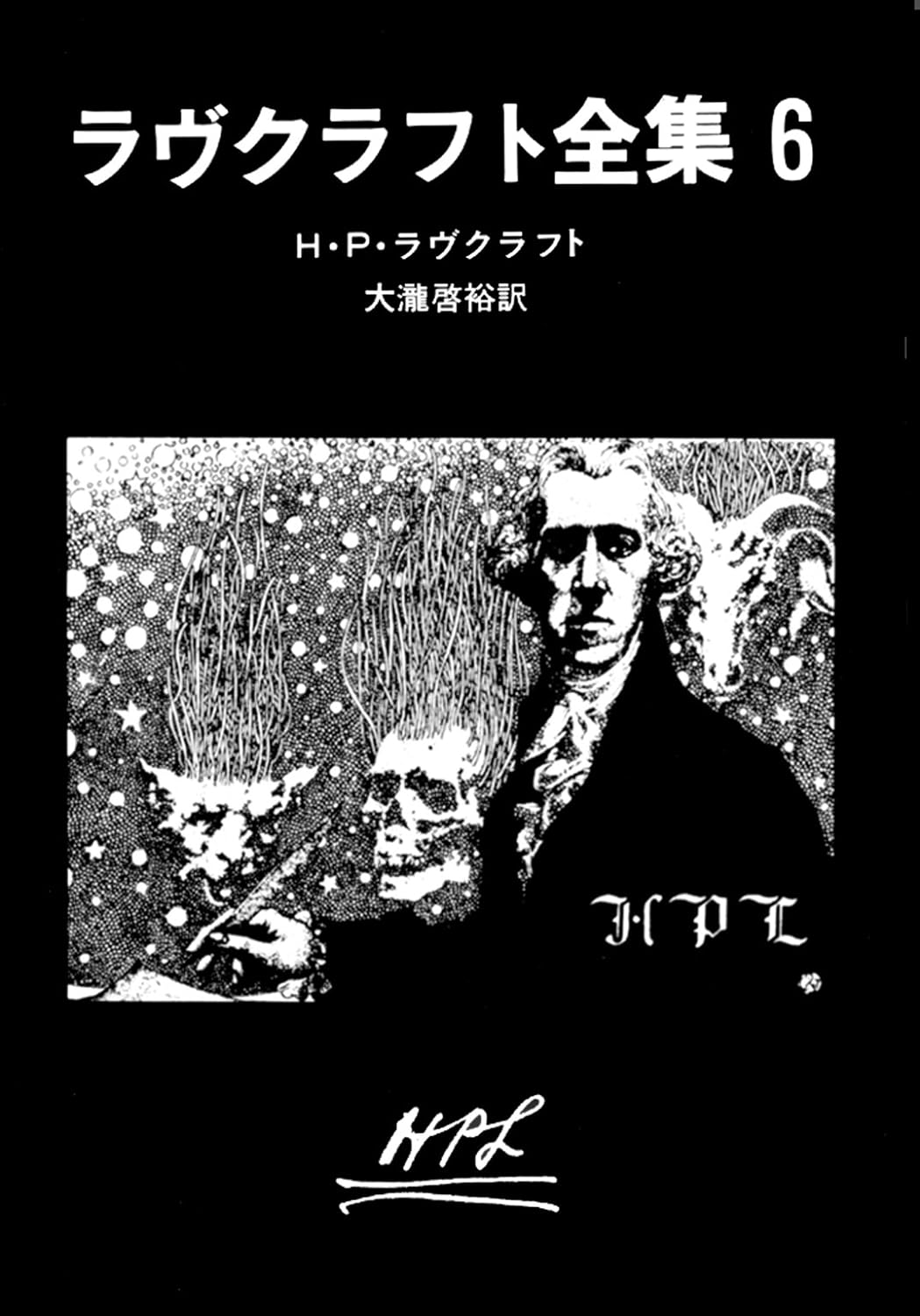
『名状しがたいもの(The Unnamable)』は、H・P・ラヴクラフトが1923年に執筆し、1925年に発表した短編小説である。
本作は、形容不能な恐怖を描き出すというラヴクラフト的テーマを、自己言及的メタフィクションの形で展開しており、幻想文学に対する彼自身の批評意識が色濃く表れている作品である。
創元推理文庫の『ラヴクラフト全集6』に収録されている。
目次
注意
読者の体験を損なう可能性があるため、本解説を読む前に先に物語を読んでおくことを強く推奨する。
書籍の表紙以外に掲載しているイラストはあくまで本ブログによる創作物であり、公式に発表されているものではない点に注意して頂きたい。
物語の概要

物語の舞台はマサチューセッツ州アーカムである。
この町は、ラヴクラフトが創造した架空のニューイングランド地方の都市であり、後の作品群に頻繁に登場する。
語り手であるカーター(のちにランドルフ・カーターと同一視される)が登場し、友人である懐疑論者のジョエル・モントアーニー牧師とともに、アーカムの古い墓地を訪れる場面から物語は始まる。
カーターは作家であり、幻想文学や怪奇小説の執筆をしている。
彼は、「この世には名状しがたい存在があり、それを描写しようとする言葉の限界がある」と語り、それに対してモントアーニーは理性的な懐疑を表明する。
二人は墓地の隣にある古い廃屋にまつわる怪談について語り合う。
この廃屋には、かつて「名状しがたいもの」が棲んでいたという伝承があり、忌まわしい形容もできない姿をした怪物が地元では語られてきた。
議論のさなか、二人は夕暮れから夜にかけて墓地で過ごすが、突如として説明不能の存在による襲撃を受け、意識を失ってしまう。
カーターは病院で目を覚まし、全身の傷とともに事態を把握しようとするが、驚くべきことに、合理主義者だったモントアーニーが「あの名状しがたいものを見た」と語る。
モントアーニーによれば、それは骸骨のようで、目がぎらぎらと輝き、山羊に似た角をもち、惨劇のうちに死んだ何世紀も前の忌まわしい子孫の姿をしていた。
それは人間とも幽霊ともつかない異様なものであったが、間違いなく実在し、言語では説明不可能な恐怖そのものであった。
登場人物
カーター(Carter)

語り手であり、おそらくランドルフ・カーターと同一人物。
幻想文学作家であり、形容不能なものの存在を信じている。物語においてはラヴクラフト自身の思想を強く反映した人物である。
ジョエル・モントアーニー(Joel Manton/Montaigne)
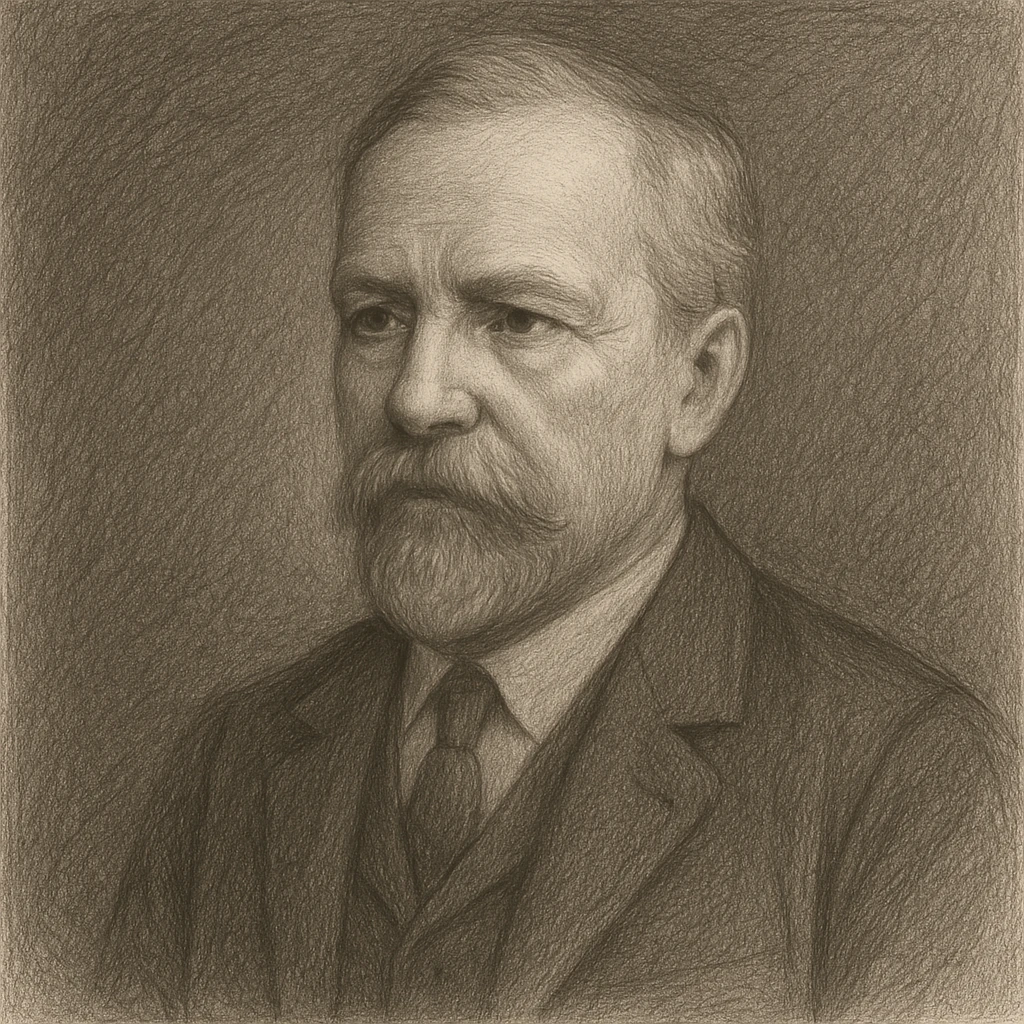
牧師であり、理性と論理を重んじる懐疑主義者。
物語冒頭ではカーターの語る超自然を一蹴するが、終盤で「名状しがたいもの」と接触し、信念が揺らぐ。
地名
アーカム(Arkham)

架空のニューイングランドの町で、古くから魔女や幽霊の伝承が残る神秘的な場所。
本作をはじめ、後のクトゥルフ神話作品においても頻出する中核都市である。
古い廃屋と墓地

名状しがたいものの根城とされる場所。
かつて忌まわしい血を引く人間が住んでいたとされるが、世代を経て非人間的存在へと堕したとも伝えられる。
解説
『名状しがたいもの』は、恐怖の本質とは何か、言語によって恐怖はどこまで表現可能かというテーマを根底に据えたメタ的な作品である。
作中で語られる「名状しがたいもの」は、視覚的・触覚的な情報をもってしても言葉にできないという性質を持ち、ラヴクラフトが創作活動を通じて追求した「宇宙的恐怖(cosmic horror)」の原型である。
また本作は、幻想文学における写実と抽象の対立、あるいは合理主義と神秘主義の対比を、カーターとモントアーニーの対話を通じて表現している。
最終的に懐疑論者が「見てしまう」ことで価値観を崩壊させられる点において、恐怖の本質は「知識にある」のではなく、「経験にある」というラヴクラフト的真理が提示されている。
言葉では到底説明しえないもの、それが名状しがたいもの(the Unnamable)であり、ラヴクラフトの恐怖文学において、最も純粋かつ抽象的な怪物であるといえよう。