『壁のなかの鼠(The Rats in the Walls)』(H.P.ラヴクラフト著)の解説
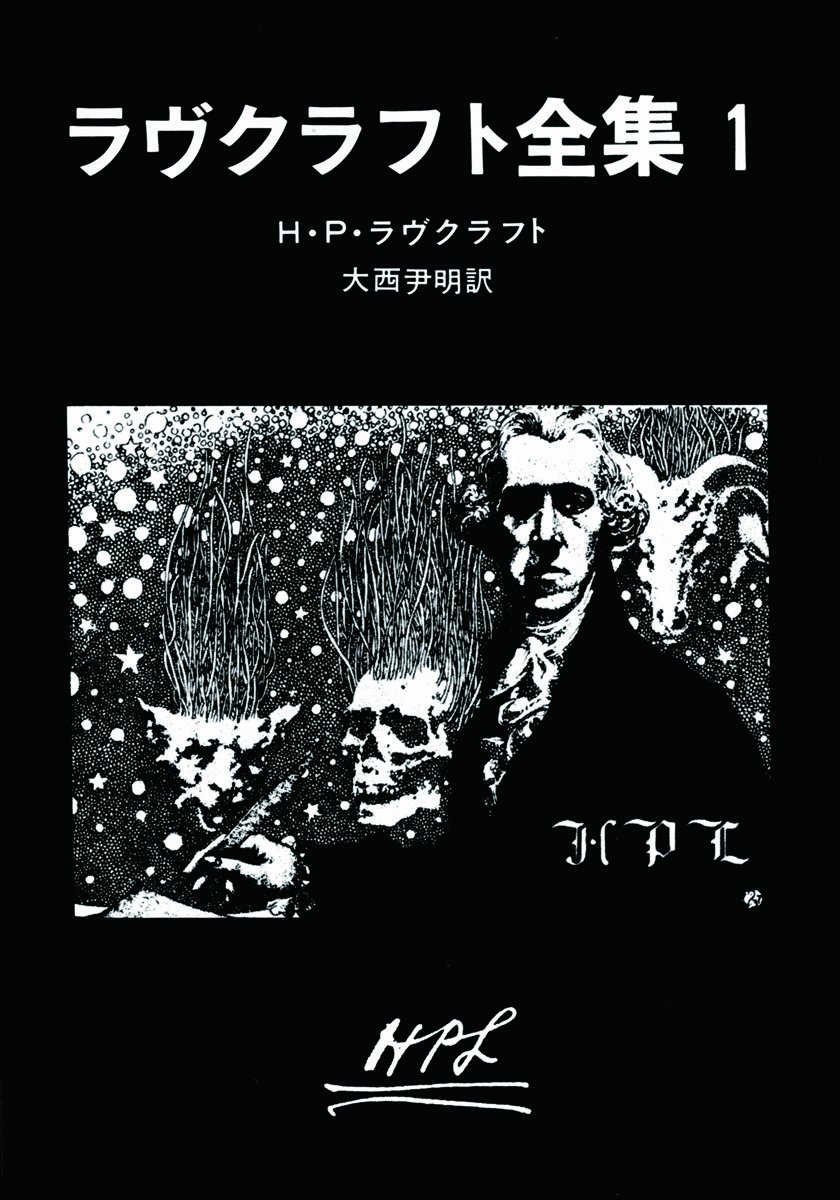
『壁のなかの鼠(The Rats in the Walls)』は、1923年に執筆されたラヴクラフトの代表的ゴシック・ホラー作品である。
目次
注意
読者の体験を損なう可能性があるため、本解説を読む前に先に物語を読んでおくことを強く推奨する。
書籍の表紙以外に掲載しているイラストはあくまで本ブログによる創作物であり、公式に発表されているものではない点に注意して頂きたい。
物語概要
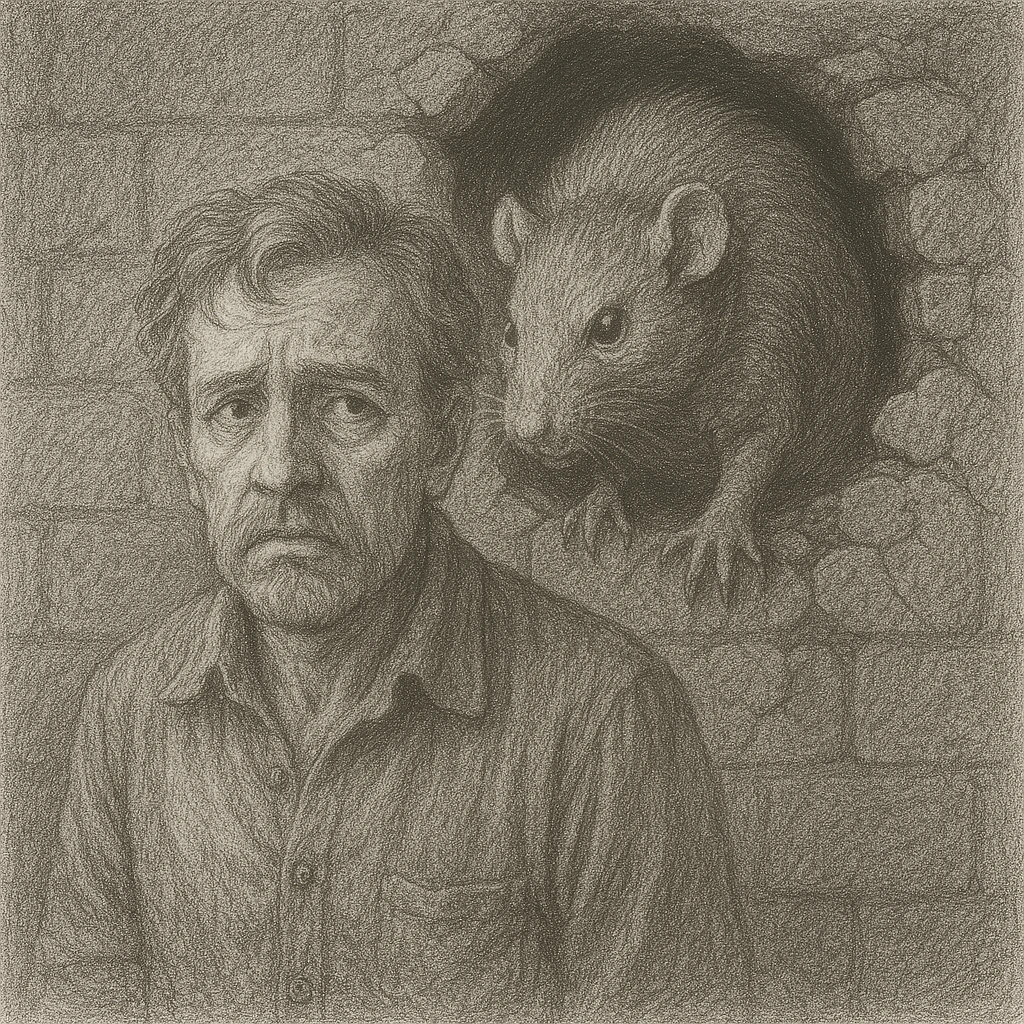
本作は、祖先の住んでいたイギリスの古邸宅を修復した語り手が、壁の中を走り回る鼠の音を聞いたことをきっかけに、恐るべき過去に直面するという筋立てを持つ。
主人公はアメリカ人で、イングランドのイグザム地方にある先祖伝来の邸宅「デ・ラ・ポール館」を購入・修復して移り住む。
この館は17世紀に忌まわしい事件があって以来、長く無人であり、地元では不吉な伝説に包まれていた。
主人公は猫「黒すけ」を伴い、修復を終えた館での新生活を始めるが、まもなく夜な夜な「壁の中の鼠」の騒音に悩まされるようになる。
この異常現象は主人公と猫にしか感知できず、やがて主人公は、壁の内にある古い石壁や、地下に潜む秘密の構造物の存在に気づく。
探索を進めるうちに、地下のさらに下には、人間が獣化して飼育・捕食されていた地下世界が存在し、主人公の一族が古代からそのような儀式的な行為を続けていたことが明らかになる。
物語の最後で、主人公は精神を喪失し、猫の「黒すけ」に導かれるように、遺伝の血に従って狂気に陥る。
主な登場人物
主人公(デ・ラ・ポール家の末裔)
本名は語られない。アメリカに住んでいたが、祖先の館を修復し、イギリスに移住する。
家系の過去を知るにつれ、次第に狂気へと沈んでいく。
黒すけ(Nig)
語り手の飼い猫であり、物語の鍵を握る存在。
鼠の気配を鋭く察知し、しばしば地下へと導く役目を果たす。
ノリス大尉
地元の地主で、語り手に協力する好古家。
最終的には地下での恐怖体験により命を落とす。
ソーントン博士
霊的現象を研究する学者。
探索に同行し、遺構に残された碑文を解読する。
主な地名と用語
イグザム修道院跡
語り手の先祖の館が建てられている土地。
古代ローマ時代からの建築が地中に残り、異教的な儀式が行われていた痕跡が発見される。
地下迷宮・納骨所
館の下に広がる地下構造で、人間や獣の骨が散乱する地獄のような空間。
壁にはラテン語の碑文が刻まれており、「アティス神」などの異教神への言及がある。
鼠(ラット)
表面的にはただの鼠に見えるが、物語を通じて、超常的な存在、あるいは過去の記憶と血の遺産の象徴とされる。
最終的には、語り手を過去と狂気へと導く媒体である。
考察
『壁のなかの鼠』は、ラヴクラフトが得意とした「家系に潜む忌まわしい血の記憶」「地下に眠る異界の記録」「不可視の存在の恐怖」といったテーマを網羅する作品である。
特に、現代的合理主義と遺伝・本能の相克が根底にあり、語り手が最終的に「先祖の行い」を再現してしまう点は、ラヴクラフトの運命論的恐怖観を象徴している。
また、黒猫「黒すけ」の行動は、本能的な真実の感知者としての役割を担っており、人間には感知できない恐怖がこの世に存在することを示す装置となっている。
本作は、ラヴクラフト作品の中でも文学的完成度が高く、オカルト的暗示とゴシック的情景、古代文明への崇拝が見事に融合している。
ホラー文学としてはもちろん、クトゥルフ神話の「古の地下遺構」モチーフの起源の一つとしても重要な位置づけにある。