『蕃神(The Other Gods)』(H.P.ラヴクラフト著)の解説
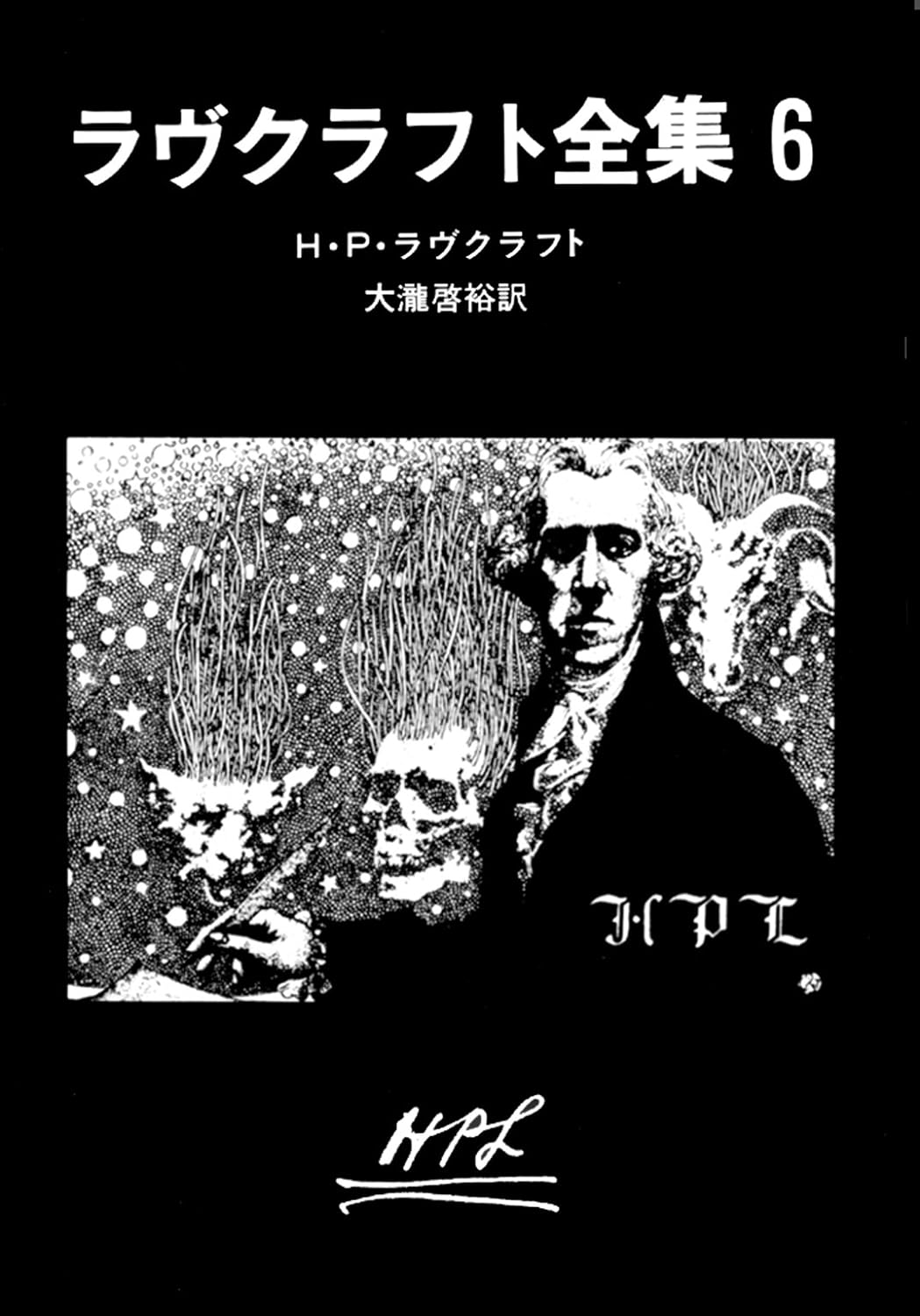
『蕃神(ばんしん)』(原題:The Other Gods)は、H・P・ラヴクラフトが1921年に執筆した短編小説であり、神々の住む高みへの傲慢な接近が招く破滅を描いた寓話的な物語である。
ラヴクラフトの夢幻的な宇宙観と、「人間の知識欲と神秘の禁域」という主題が濃厚に表現された作品であり、後の『未知なるカダスを夢に求めて』などと共通する世界観を備えている。
創元推理文庫の『ラヴクラフト全集6』に収録されている。
目次
注意
読者の体験を損なう可能性があるため、本解説を読む前に先に物語を読んでおくことを強く推奨する。
書籍の表紙以外に掲載しているイラストはあくまで本ブログによる創作物であり、公式に発表されているものではない点に注意して頂きたい。
物語の概要

舞台は幻想世界の遥かなる山岳地帯、特に神々のかつての居住地であるハテグ=クラの山である。
この山は「大地の神々(the Great Ones)」がかつて棲まっていたとされる聖地であり、現在では人間の接近を禁じられた地である。
神々は、俗世から逃れて現在は「未知なるカダス」の凍てつく荒野に身を潜めているが、夜な夜な懐かしき山々を訪れては舞い戯れるとも言われる。
主人公は、神秘学の大家であり、深い学識を有する老人バルザイである。
彼は『フサンの謎の七書』や『ナコト写本』などの古文献を読み込み、大地の神々について並外れた知識を得ていた。
そしてついに、禁忌を破って神々の姿をその目で見ようと、弟子である若き神官アタルを伴って、神々の住まいであるハテグ=クラの頂上を目指して登山を開始する。
登山の道中、アタルは不安と畏れを抱き、村人たちの忠告もあったが、バルザイは学問と経験に裏打ちされた自信によってそれらを無視し、神々に対する傲慢な確信を示す。
彼はついに霧のかかった月夜、神々が現れるという刻に頂上に至り、神々の姿を見たと叫ぶ。
しかしその瞬間、彼の前に現れたのは大地の神々ではなく、蕃神(the Other Gods)であった。
蕃神とは、大地の神々を超越する外なる恐怖の存在であり、神々の領域を冒そうとする者に罰を与える、名状しがたい存在である。
蕃神は異形の存在であり、怒りを抱いて天空から降臨し、神々を覗こうとしたバルザイに制裁を加える。
彼は叫びながら姿を消し、二度と人前に現れることはなかった。
のちに村人たちがハテグ=クラを登ると、山頂の石に異形の巨大な刻印が残されており、それは『ナコト写本』の恐ろしい章に描かれた禁断の印と一致していた。
バルザイの運命について語る者はいなかったが、彼の末路が「蕃神の怒り」を象徴するものとなったことは明白である。
登場人物
バルザイ(Barzai the Wise)
賢者、神秘学者として知られた老人。
神々の秘密に通じていたが、その知識は慢心となり、禁を破って神々の姿を見ようとした。
最終的に蕃神によって消滅させられる。
アタル(Atal)
宿屋の主人の息子で、若き神官。
バルザイの弟子として登山に同行するが、神々の姿を見るには至らず、無事に山を下りた後は聖職者として生涯を送る。
大地の神々(the Great Ones)
人間に比較的親しい神々で、夢の世界や山に住む。通常は人間に直接関与せず、姿を見ることは許されていない。
蕃神(the Other Gods)
外なる地獄の存在。大地の神々をも超える力を持ち、人間が神の領域を犯すことを決して許さない。
姿も本性も名状しがたく、プレゲトーンのような冥界の象徴でもある。
地名
ハテグ=クラ(Hatheg-Kla)
神々がかつて住んだとされる霊峰。
ハテグの地の奥に位置し、常に霧に覆われ、神々の舞いが行われると言われる聖なる山である。
ウルタール、ニル、ハテグ
バルザイとアタルの出発点であり、大地の神々の伝説が残る地。『ウルタールの猫』など、他のラヴクラフト作品でも登場する場所である。
解説
本作は、人間の知識欲と傲慢さに対する警鐘である。
バルザイは知識を深めることで神の領域に到達できると信じていたが、それは人間に許されない禁忌であった。
ラヴクラフトが一貫して描く「宇宙的恐怖(cosmic horror)」、すなわち、人間の理性では測れない力と無知の深淵がここでも中心に据えられている。
「蕃神」という存在は、クトゥルフ神話における外なる神々(Outer Gods)の先駆けであり、ナイアーラトテップなどの後のキャラクターに繋がる要素を持つ。
大地の神々が人間に比較的近い存在であるのに対し、蕃神は完全に異質で容赦がなく、徹底して人間を無力な存在として扱う。
バルザイの運命は、ラヴクラフト作品における典型的な警句であり、「知られざるものを覗くな」「神秘のヴェールを剥がすな」というメッセージが強く刻まれている。
彼の最期の叫びは、人知を超えるものの恐怖を象徴しており、その声はあらゆる知識と探求への「代償」を如実に示しているのである。