『サルナスの滅亡(The Doom That Came to Sarnath)』(H.P.ラヴクラフト著)の解説
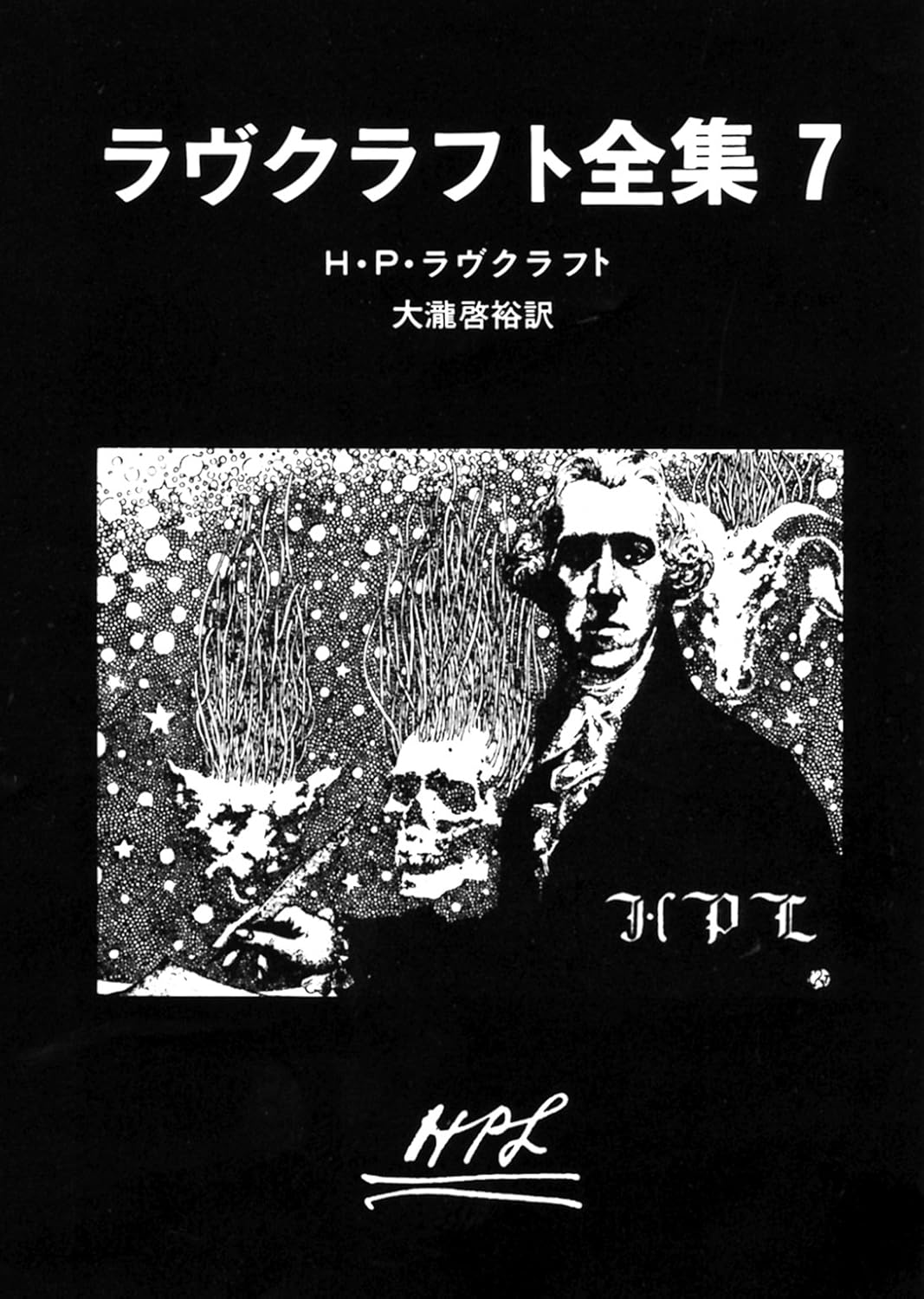
『サルナスの滅亡(The Doom That Came to Sarnath)』は、H・P・ラヴクラフトによる幻想的な短編であり、彼の初期作品のひとつである。
物語は、太古の神秘的な土地「ムナール」における都市サルナスの誕生と栄華、そして最終的な破滅を壮麗かつ寓話的な筆致で描いたものである。
創元推理文庫の『ラヴクラフト全集7』に収録されている。
目次
注意
読者の体験を損なう可能性があるため、本解説を読む前に先に物語を読んでおくことを強く推奨する。
書籍の表紙以外に掲載しているイラストはあくまで本ブログによる創作物であり、公式に発表されているものではない点に注意して頂きたい。
物語の概要

物語の舞台はムナールと呼ばれる幻想の地である。
この地には出口も入口もない静かな湖があり、その湖畔にはかつて「イブ(Ib)」という灰色の石造都市が存在していた。
イブには、緑色の肌に膨れ上がった目と突き出た唇を持ち、声を発することのない水棲の異形生物が棲んでいた。
彼らは月が満ちる夜に、蜥蜴神ボクラグに似せて彫られた石像の前で跳ね回るという、太古の密儀を行っていた。
やがて髪の黒い人間の部族がムナールに到来し、湖畔にサルナスという都市を建設する。
彼らはイブの異形の住人を忌み嫌い、ある日その住人を皆殺しにし、都市を滅ぼした。
その際に残ったボクラグの石像だけを持ち帰り、サルナスの神殿に安置したが、その夜、大神官タラン=イシュが死に至り、祭壇には破滅を予告する印が刻まれていた。だが、それもすぐに忘れ去られる。
サルナスはその後、千年にわたり黄金の都市として栄え、軍事、芸術、建築において比類なき発展を遂げる。
しかし、イブ滅亡千年の祝宴の夜、湖から立ち昇った緑の霧とともに異変が起こる。
城門が開き、都の民が狂乱状態で逃げ惑い、「黄金の大皿の前に緑の怪物が跳ね回っていた」と口々に叫んだ。
翌朝、訪問者たちが見たのは、広大な湿地と蜥蜴が這う光景だけであり、サルナスの跡形は完全に消滅していた。
登場人物
ボクラグ(Bokrug)
イブの民が信仰していた水棲の蜥蜴神であり、最後にサルナスを滅ぼした超自然的存在とされる。
その石像だけが終盤で再び発見される。
タラン=イシュ
サルナス最初の大神官であり、石像を神殿に安置した夜に恐怖のうちに死亡し、祭壇に破滅の徴を記した。
ナルギス=ヘイ
千年後の祝宴を主催したサルナスの王。
宴の最中に異形の者たちに取り囲まれ、都とともに消滅する。
地名
ムナール
物語全体の舞台となる土地で、複数の都市(トゥラー、イラーネク、カダテロンなど)を擁している。サルナスはその中心的な存在であった。
サルナス
物語の主舞台となる湖畔の大都市で、建築・美術・学問において頂点を極めた文明都市。
豪奢な神殿、宮殿、庭園がそびえ立ち、貴金属や文化が集約されていた。
イブ(Ib)
サルナス建設前から湖畔にあった灰色の都市。
住民は異形の水棲種族であり、ボクラグを崇拝していたが、サルナスの民によって虐殺され、都市も滅ぼされた。
アクリオンの岩
湖畔にそそり立つ灰色の岩で、サルナス滅亡の際に水没し、象徴的な役割を果たす。
解説
本作はラヴクラフトが影響を受けたダンセイニ卿風の幻想的な文体で書かれ、クトゥルフ神話の要素は希薄ながらも、後の神話構築の土台となる神名や雰囲気が散見される。
サルナスの民が異種族を滅ぼし、その報復として都市全体が神罰のごとく消滅するという構図は、「傲慢と崩壊」という古典的な寓話の形をとっている。
また、滅亡の前夜に繰り広げられる祝宴の描写と、突如訪れる破滅との対比が読者に強烈な印象を与える。
幻想文学としての完成度が高く、無名の神々、古代の遺物、超自然的存在による復讐といった、ラヴクラフトが後に発展させるテーマの原点がここにある。